SWOT分析とは?現役リサーチャーが最重要フレームワークを徹底解説
あなたの会社では、戦略を立てる前に、どのような基準で意思決定をしていますか?
経験則に頼った判断や前年度の方針をそのまま踏襲していないでしょうか。こうした手法では、市場の急激な変化に柔軟に対応するのは難しくなります。
そこで注目されているのがSWOT分析です。
これは強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4軸をもとに、企業の内外の状況を構造的に整理し、戦略の方向性を導くフレームワークです。
とはいえ、SWOT分析は単に表を埋めるだけの作業ではありません。重要なのは、得られた情報をどう解釈し、将来の意思決定に結びつけるかという視点です。分析から行動へとつなげる力こそが、SWOTの本質です。
本記事では、SWOT分析の基本概念から、戦略への具体的な落とし込み方、実務に活かすための手順までを詳しく解説します。分析を机上の空論で終わらせないための実践知をご紹介します。
SWOT分析とは
SWOT分析とは、自社の内部環境である「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」、外部環境である「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」の4要素を洗い出し、戦略立案の土台を築くための手法です。フレームワーク自体はシンプルですが、価値があるのは分類することではなく、どう活用するかという視点にあります。
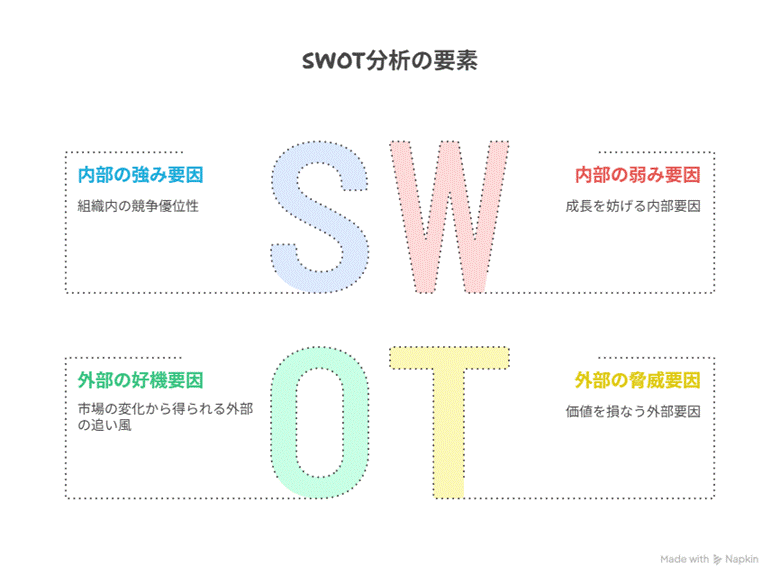
たとえば、自社の強みと市場の機会を掛け合わせることで、どの領域に成長の可能性があるかを導き出せます。一方で、弱みと脅威の組み合わせからは、どこにリスクが潜んでいるかを可視化できます。
重要なのは、分類で終わらせず、そこから仮説を立て、行動へと結びつける視点を持つことです。
この分析は、経営層だけでなく、事業部門やマーケティング、営業、商品企画など、あらゆる現場で活用できます。
SWOT分析の目的
事業戦略を見直すとき、今あるリソースで何ができるか、どこに脅威が潜んでいるかを正しく把握することは欠かせません。SWOT分析の目的は、こうした経営判断の前提を整えることにあります。ただ情報を分類するのではなく、戦略につながるインサイトを得ることこそが本質です。
以下では、SWOT分析の3つの目的を整理します。
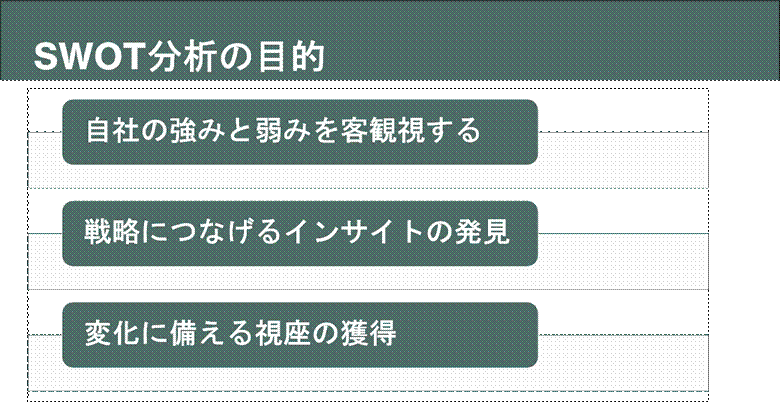
自社の強みと弱みを客観視する
SWOT分析の第一の目的は、自社の強みと弱みを冷静に見つめ直すことです。
私たちは過去の成功体験に引きずられ、強みを過信してしまうことがあります。また、弱みに対しても、いずれ解決できると楽観的に捉え、現実から目を背けてしまう傾向があります。
たとえば、かつては強みとされていた顧客基盤が、現在では高齢のリピーター層に偏っているといったケース。あるいは、IT人材が慢性的に不足しているにもかかわらず、対応を先送りにしたまま、成長の足かせになっていることもあります。
SWOT分析を通じて、こうした思い込みや曖昧な評価を排除し、現在の自社の立ち位置を明確にすることが可能です。とくに、社外の視点を取り入れることで客観性が高まり、より実効性のある戦略立案につながります。
戦略につなげるインサイトの発見
SWOT分析の本当の価値は、四つの要素をそれぞれ整理することではありません。
重要なのは、それらを組み合わせて、どのような戦略仮説を導けるかを考える視点にあります。いわゆるクロス分析と呼ばれる手法によって、戦略に直結する洞察を得ることが可能になります。
たとえば、自社の強みと市場の機会を掛け合わせれば、成長の起点となる攻めの戦略が浮かび上がるでしょう。一方、弱みと脅威を重ねて見ることで、早急に手を打つべき守りの戦略が明確になります。
実際の例としては、ブランド力を強みに持つ企業が、新興国市場の拡大を機会と捉え、現地に特化したプレミアム路線で差別化を図るといった戦略があります。
このような掛け合わせの発想により、単なる現状把握では得られない示唆を得られるのです。
変化に備える視座の獲得
SWOT分析における機会と脅威は、単に外部環境を並べるための項目ではありません。重要なのは、そこから何を読み取り、どのような未来に備えるかという視点を持つことです。
不確実性の時代、いわゆるVUCAの環境下では、過去の成功体験や現在のデータに頼った判断だけでは、大きなリスクにつながりかねません。
たとえば、サステナビリティへの関心が社会的に高まっている状況は、新たな機会としてESG対応製品の開発を後押しする要因になります。一方、生成AIの急速な進化は、自社の中核サービスが数年以内に代替される可能性を含んでおり、見過ごせない脅威となり得ます。
こうした変化の兆しに対して、早い段階で対応の選択肢を持っておくことが、将来的な柔軟性と対応力を高めます。
脅威とは、まだ発生していないものの、起きた場合に深刻な影響をもたらす潜在的なリスクです。つまり、今は問題ないと楽観するのではなく、次に何が起こり得るかを考えることが、SWOT分析を未来志向の戦略へと昇華させます。変化に備えるとは、単なるリスク回避ではなく、次の一手を設計するということです。
SWOT分析の重要性
SWOT分析は、自社の立ち位置を確認する地図であると同時に、未来に向けた戦略の原型を描く設計図でもあります。
その本質は、強み・弱み・機会・脅威という四つの要素を、個別に捉えるのではなく、関係性の中で捉えることです。情報を並べるだけでは意味はなく、それぞれの交差点で何が起こり得るかを仮説として組み立てることに価値があります。
たとえば、ある強みはどの機会と結びつき、どのような戦略の可能性を生むのか。あるいは、特定の弱みが脅威と組み合わさったとき、どのような事態が想定されるのか。こうした問いに向き合う過程で、自社にしか導き出せない戦略仮説が立ち上がってきます。
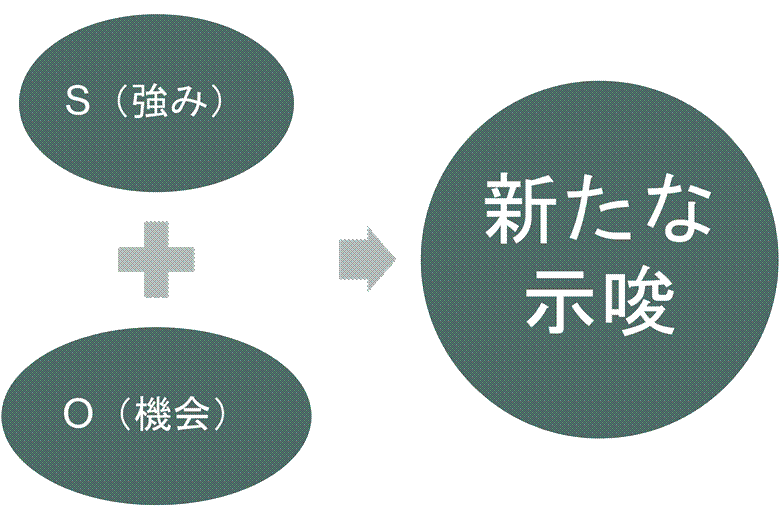
ここで見落としてはならないのは、SWOTの各要素は一見、過去や現在の情報に見えて、実は未来の意思決定のために存在しているという点です。
なかでも脅威は、悲観すべき要因ではなく、それが現実になったとき、自社がどう振る舞うべきかを設計するきっかけとなります。つまりSWOT分析とは、現状の棚卸しを目的とするのではなく、目指すべき未来から逆算して、今とるべき行動を導き出すための思考法です。
構造的な変化にどう対応するか、経営資源をどこに配分するかといった戦略の骨格を、論理的かつ具体的に設計するための土台となります。
SWOT分析が有効な4つのシーン
SWOT分析は、どのような場面で使うと最大の効果を発揮するのでしょうか。とりあえずやってみるという形で導入されがちですが、本来は明確な意思決定のタイミングでこそ真価を発揮するフレームワークです。
ここでは、戦略設計の実務においてSWOT分析が特に有効な4つのシーンを紹介します。
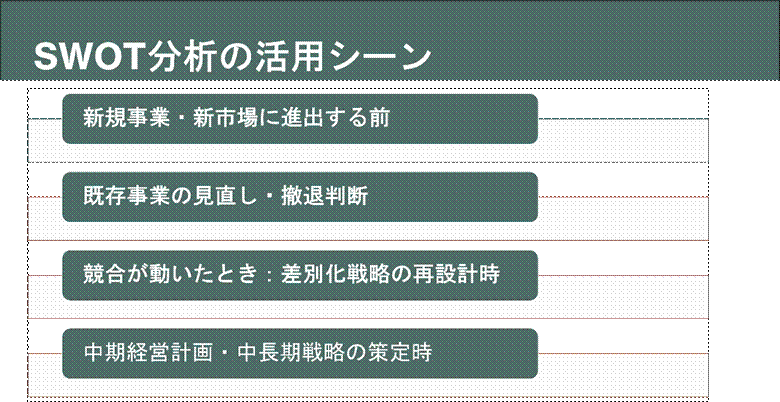
新規事業・新市場に進出する前
新たな領域に踏み出す際に問うべきなのは、「できるかどうか」ではありません。
重要なのは、何を強みとして、どこで、どう勝つのかを見極める視点です。SWOT分析を活用すれば、自社の持つ資源が転用可能かどうか、また競争優位を保てる環境が整っているかを具体的に把握できます。
たとえば、自社が長年にわたり培ってきた技術や人材、顧客基盤は、新市場においても通用するのか。それとも、その市場では価値を持たない資産にすぎないのか。さらに、競合の参入障壁が高く、コスト構造の違いが脅威となる場合は、無理な挑戦がリスクにつながる可能性もあります。
新規市場は一見すると魅力的に映りますが、強みが通用しない環境に無策で進出すれば、資源を浪費する結果に終わりかねません。だからこそ、進出の可否を問うのではなく、どの土俵で戦えば自社の強みが活きるのか。その設計こそが、SWOT分析によって明らかになります。
既存事業の見直し・撤退判断
この事業を本当に続けるべきか。
この問いに向き合うことは、経営における最も難しい判断のひとつです。売上が立っていたり、長年にわたって継続してきた事業であったりすると、感情や慣習が判断を曇らせることがあります。しかし、構造的に衰退が進んでいる事業を続けることは、将来の企業全体の足かせになりかねません。
そこで有効なのが、SWOT分析による冷静な現状評価です。
かつては競争優位の源泉だった強みが、市場の成熟や標準化によって埋もれてしまっていないか。あるいは、長年放置されてきた弱みが、成長の妨げとなっていないか。こうした点を客観的に棚卸しすることで、撤退を検討すべきシグナルが明確になります。
さらに、市場構造そのものが変化している可能性にも目を向ける必要があります。
市場が縮小傾向にある、顧客ニーズが明確に変化している、代替手段が次々に登場している。
こうした変化が脅威として顕在化したとき、自社に対応策がなければ、早期の撤退判断が将来の損失を回避する手段となります。今は黒字だからやめられない、と思っていても、数年後には赤字へと転じている可能性もあります。
SWOT分析は、そうした兆候を感情や目先の数字ではなく、構造的な視点で捉えるための有効なレンズになります。
競合が動いたとき:差別化戦略の再設計時
戦略の成否は、自社の施策だけでなく、競合の動きにも大きく左右されます。とくに注意すべきなのは、自社の強みが競合の一手によって、短期間で当たり前のものになってしまうケースです。つまり、相対的な価値が一夜にして失われることもあるのです。
たとえば、高度な技術力やスピーディなカスタマーサポートといった差別化要素も、競合が同様の体制を整えた時点で、優位性ではなくなります。さらに視点を広げれば、自社の戦略が競合にとっての新たな機会になっていないか、すなわち、自社の強みが他社の成長の足がかりとなっていないかという逆方向の関係にも注目すべきです。
こうした競争環境の変化が起きたとき、従来の戦略をそのまま続けていては通用しない可能性があります。競合の動きによって脅威が顕在化した場合には、自社の強みや弱みの意味そのものが構造的に変わってしまうこともあります。その際には、単なる施策の調整ではなく、自社の立ち位置を再定義する必要があります。
SWOT分析は、競合によって変化した市場構造に対応し、自社の再設計を行うための出発点になります。環境が変わったあとにどう動くか。その判断を冷静に下すために、SWOTは極めて有効な戦略ツールです。
中期経営計画・中長期戦略の策定時
数年先を見据えた戦略を設計するうえで、SWOT分析は現実認識と仮説構築をつなぐ重要な架け橋となります。中期経営計画や中長期戦略では、現在の資産だけでなく、それが将来どのように変質しうるかまでを視野に入れる必要があります。
たとえば、今は競争力の源泉となっているテクノロジーが、5年後には時代遅れのレガシーシステムになってしまうリスクがあります。また、今は強みと見なされている資産が、成長分野への対応が遅れることで、やがては負債と化す可能性もあります。
こうした兆候を早期に捉え、資源配分を先手で見直すには、内部の強みや弱みと、外部の機会や脅威を同時に把握できるSWOT分析が不可欠です。
加えて、技術トレンド、法規制の変化、社会構造の変動など、将来のゲームチェンジとなり得る要因に着目することで、戦略仮説に現実味を持たせることができます。単に数字を積み上げる計画ではなく、変化を前提にした柔軟な意思決定が可能になります。
SWOT分析は、現在の課題と未来の不確実性を同時に扱える数少ないフレームワークです。だからこそ、中期的な視点で戦略を立てる場面において、冷静な現状把握と優先順位づけ、そして複数のシナリオを描くための有効な基盤となります。
失敗しないSWOT分析の手順
SWOT分析はシンプルなフレームワークであるがゆえに、形だけをなぞって終わってしまうケースが少なくありません。表を埋めること自体が目的化してしまい、分析結果が戦略に活かされない、そんなあるあるに陥らないためには、思考の順序と問いの立て方が極めて重要です。
ここでは、実践で機能するSWOT分析を行うための6つのステップを紹介します。
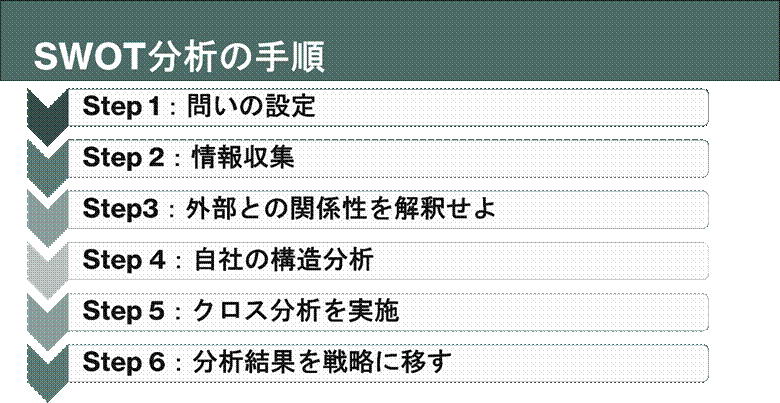
Step 1:問いの設定
SWOT分析の出発点は、何を成功させたいのかを明確にすることにあります。分析の対象が企業全体なのか、特定の事業領域なのか、あるいは個別プロジェクトなのか。この前提が曖昧なまま進めると、情報が拡散し、意味のある示唆を導き出すことができません。
たとえば、中期経営計画の策定、新規事業の実行可否の判断、サービス撤退の検討など、分析の目的を具体的に設定する必要があります。勝負すべき相手は誰か、どのような結果を勝ちと定義するのか。それが明確でなければ、SWOTは単なる情報整理で終わってしまいます。
Step 2:情報収集
SWOT分析の精度を左右するのは、分析に入る前にどれだけ多様で質の高い情報を収集できるかにかかっています。
内部情報については、財務指標だけでなく、人材構成や組織の再現性、顧客からの評価といった、目に見えにくい構造的な強みや弱みを把握する視点が不可欠です。
【主な内部情報】
| 項目 | 内容 | 本質的な意味 |
| 業績・財務データ | 売上、利益、原価構造、利益率、LTV、CAC | 数字で測れない強みは、主観に過ぎない |
| 人材構成 | 専門職の比率、離職率、年齢構成、リーダー層の質 | 組織のケイパビリティ(実行力)は人材に宿る |
| オペレーションの再現性 | 自動化率、属人化の度合い、ツール導入状況 | 強みが再現可能かどうかを見極める必要がある |
| 顧客満足度・解約率 | NPS、CSスコア、Churn率 | 顧客が強みとして認識しているかどうかの裏付けが得られる |
| 営業・マーケティング指標 | CVR、商談化率、案件化リード数、リードソース | 弱みがどこに集中しているかを特定できる |
一方、外部環境の把握では、市場規模や成長率、制度変更、技術トレンドなどの定量データに加え、競合の動向や顧客ニーズの変化といった定性的情報の収集が欠かせません。これらを網羅的に集めることで、思い込みを排除し、バランスの取れた分析が可能になります。
【主な外部情報】
| 項目 | 内容 | 本質的な意味 |
| 市場規模・成長率 | TAM、SAM、SOM、成長トレンド | 機会の大きさは市場の規模と伸び率で決まる |
| 法規制・制度改正 | 業界ルール、参入条件、補助金 | 法制度の変化は、機会にも脅威にもなる |
| 技術トレンド | 新技術の商用化進度、ディスラプターの出現 | 既存モデルが陳腐化するリスクを早期に把握する |
| 競合情報 | 他社の製品、価格、シェア、人材確保状況 | 自社の強みや弱みを相対化するための絶対条件 |
| 顧客インサイト | ペルソナの変化、購買要因、ニーズの移行 | 機会は、顧客のまだ満たされていない欲求の中に存在する |
Step3:外部との関係性を解釈せよ
SWOT分析における機会と脅威は、単なる外部情報の羅列ではありません。これらは、自社の構造や前提とどのように関係しているかによって、はじめて意味を持ちます。
たとえば、脱炭素化の潮流は一見すべての企業にとっての脅威に見えるかもしれませんが、すでに再生可能エネルギー分野に取り組んでいる企業にとっては、成長を後押しする要因にもなります。このように、外部環境そのものは中立的であり、それをどう解釈するかが戦略の方向性を決めるのです。
この段階では、PEST分析や5フォース分析といった他のフレームワークも併用しながら、「この環境要因は、自社の強みを強化するか」「弱みをより深刻にするか」といった視点で検討を重ねます。重要なのは、出来事そのものではなく、それが自社のビジネス構造にどのような影響を与えるかを見極めることです。
Step 4:自社の構造分析
次に向き合うべきは、自社の内部構造です。この段階で注意したいのは、単なる資産の棚卸しで終わらせないことです。
何を持っているかではなく、なぜ勝てているのか、なぜ成長できていないのかといった構造的な問いに踏み込む必要があります。
強みとは、単に優れている要素を指すのではなく、模倣されにくく、かつ将来にわたって有効性を保つものです。たとえば、特定の技術を保有していたとしても、他社が容易に再現できるのであれば、それは競争優位とは言えません。ブランド力や顧客基盤についても、今後の市場環境において価値を維持できるかが問われます。
一方、弱みとは現在の課題ではなく、成長を制限している構造的な要因です。
たとえば、人的リソースの偏在、属人化された業務プロセス、ボトルネックを放置する組織文化など、表面的には見えづらいが、長期的に足を引っ張る要素が存在します。
このステップでは、「なぜ勝っているのか」「なぜ変われていないのか」といった問いを通じて、自社の本質的な強みと弱みを掘り下げていきます。
Step 5:クロス分析を実施
ここでようやく、SWOTの四象限を掛け合わせるクロス分析に入ります。これは、以下の四つの組み合わせを軸に、戦略仮説を導き出す工程です。
- 強み × 機会:どの領域で爆発的な成長を目指すべきか
- 強み × 脅威:外部の脅威に対して、自社の強みをどう活用するか
- 弱み × 機会:成長のチャンスを逃さないために、何を補うべきか
- 弱み × 脅威:どの領域が最も脆弱で、優先的に対処すべきか
ここで重要なのは、何をやるかを決める前に、何をやらないかを明確にすることです。戦略とは、選択肢を増やすことではなく、優先順位をつけ、リソースを集中させる意思決定に他なりません。
この分析を通じて、勝負すべき領域、撤退を検討すべき事業、補強すべきケイパビリティ(組織能力)などが具体的に浮かび上がります。クロス分析は、戦略の設計図を描くための中核を担うステップです。
Step 6:分析結果を戦略に移す
多くの企業が陥りがちなのは、SWOT分析を行ったこと自体に満足してしまうことです。しかし、本来の目的は分析ではなく、そこから戦略へと落とし込むことにあります。つまり、行動や意思決定につながらなければ、どれほど精緻な分析であっても意味を持ちません。
ここで問うべきは、「この強みを、誰が、いつ、どのように活用するのか」「この脅威が現実化した場合、どのタイミングで撤退や再配置を判断するのか」といった、具体的な意思決定の設計です。役割の明確化と判断基準の設定が欠かせません。
戦略とは、構想だけでは機能せず、KPI、アクション、予算、タイムラインといった実行要素にまで落とし込まれてはじめて意味を持ちます。SWOT分析の結果は、現場の運営方針や人材配置、マーケティング施策に変換されてこそ価値があります。
SWOT分析の最終的なゴールは、経営判断の解像度を高めることにあります。単に表を埋める作業で終わるのではなく、そこから得た示唆を、現実を動かす言語と仕組みに変換することが、真の成功条件です。
SWOT分析だけで終わらない!分析結果を有効活用するポイント
SWOT分析を実施しても、「やっただけ」で終わってしまった経験はないでしょうか。
分類やクロス分析までは実施したものの、戦略や現場施策につながらない
こうした状況を回避するには、分析後の使い方に明確な指針が必要です。ここでは、SWOT分析を有効活用するために押さえるべき5つの視点を紹介します。
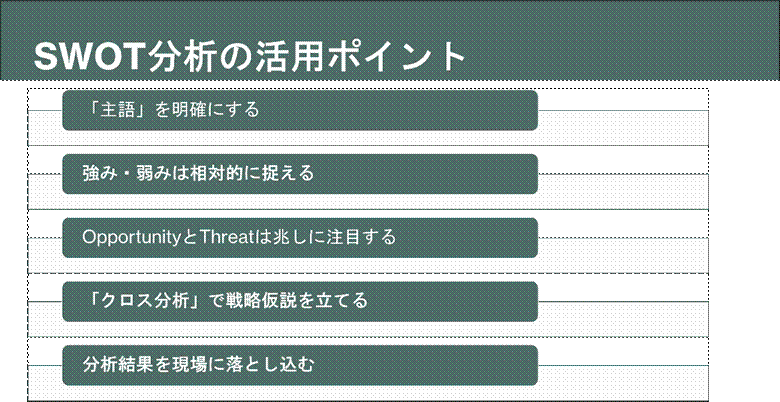
「主語」を明確にする:SWOTの対象は何か?
SWOT分析を始める際に、最初に確認すべきなのは、何を対象に分析しているのかという点です。
企業全体なのか、特定の事業なのか、それとも新規プロジェクトなのか。この前提が曖昧なままでは、分析項目が広く浅くなり、具体的な戦略に結びつかなくなります。
たとえば、企業全体を対象とする場合は、人材の質や経営基盤といった構造的な視点が中心になります。一方、特定のブランドや商品を分析するのであれば、市場でのポジショニングや販売チャネルなど、より実務に近い要素が焦点となります。
何を成功させたいのか。それを明確にする対象設定が、SWOT分析の出発点になります。
強み・弱みは相対的に捉える
自社の強みや弱みは、あくまで相対的なものであるという前提を忘れてはなりません。たとえば、技術力が高い、ブランド認知があるといった要素も、業界内ですでに標準的な水準であったり、競合の方が上回っていたりする場合は、競争優位とは言えません。
一方で、社内で課題とされている項目が、実際には業界平均と大差ないのであれば、弱みとしての優先度は下がります。
SWOT分析では、自社内の感覚だけで判断するのではなく、外部ベンチマークを活用して相対的に評価することで、より実効性のある示唆を得ることができます。
OpportunityとThreatは兆しに注目する
機会や脅威は、すでに起きている事象だけでなく、これから起きる可能性のある変化の兆しにも注目することが重要です。起こった後に対応するのではなく、兆しの段階で動けるかどうかが、戦略上の優位性を左右します。
たとえば、Z世代の価値観の変化は、既存市場の定義を見直す機会になり得ます。また、生成AIの進化は、自社の情報資産や業務の一部が数年以内に陳腐化するリスクを含んでいます。こうした変化を読み取るには、PEST分析などを併用し、外部環境の構造とその背景を把握することが有効です。
「クロス分析」で戦略仮説を立てる
SWOT分析の本質は、要素同士を掛け合わせることにあります。ただ分類して終わるのではなく、どの組み合わせに戦略の可能性があるのかを見極めることが重要です。
たとえば、
- 強み × 機会 → 競争優位を拡張するための成長戦略
- 弱み × 脅威 → リスクを回避したり、撤退を判断したりする基準
このように、各交点から行動仮説を導くことで、戦略の実行性が高まります。
クロス分析は、分析結果を並べるだけの作業ではありません。そこから経営判断に耐える選択と集中の軸を生み出すプロセスそのものです。
分析結果を現場に落とし込む
どれほど優れた分析を行っても、現場のアクションに結びつかなければ、組織は何も変わりません。SWOTで明らかになった各要素をもとに、KPI、アクションプラン、担当者、期限までを明確に設定し、戦略を業務として機能させることが求められます。
たとえば、技術人材の不足が弱みとして特定された場合には、「半年以内にエンジニア採用を強化し、研究開発の内製化比率を引き上げる」といった具体的な施策にまで分解する必要があります。抽象的な分析で終わらせず、実行に移せるかどうかが、戦略の成否を分けます。
SWOT分析に関するよくある質問
SWOT分析を初めて導入する方、または改めて活用方法を見直したい方に向けて、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
SWOT分析とは何ですか?
SWOT分析とは、企業や事業の内部要因である「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」、外部要因である「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を整理し、戦略立案の基盤をつくるためのフレームワークです。現状把握だけでなく、未来に向けた行動指針の仮説構築にも役立ちます。
SWOT分析の4つの要素は?
SWOT分析は、次の4つの要素で構成されます。
- 強み(Strength):競合優位性の源泉となる内部要因
- 弱み(Weakness):成長や競争を阻害する内部要因
- 機会(Opportunity):市場や社会の変化によって得られる外部の追い風
- 脅威(Threat):自社の価値を損なう可能性のある外部要因
SWOT分析で何を書けばいいですか?
内部要因には、業績、ブランド、人材、ノウハウ、業務プロセスなどを挙げ、外部要因には市場トレンド、競合動向、法改正、社会変化などを含めます。重要なのは、自社の戦略との関連性が高い項目を選び、「なぜそれが強み・脅威なのか」を具体的に説明できる状態にすることです。
PEST分析とSWOT分析の順番は?
一般的にはPEST分析を先に行うことで、マクロ環境の変化を整理しやすくなり、SWOT分析での「機会」と「脅威」の検出精度が高まります。PESTで抽出した外部要因をもとに、SWOTのO/T項目を定義するという流れが、より実践的です。
SWOT分析を行うために必要なデータは?
業績データ、人材構成、顧客評価、営業・マーケのKPIなどの内部情報に加え、市場規模、成長率、競合動向、技術トレンド、制度変化などの外部情報が必要です。定量情報と定性情報の両方をバランスよく収集することで、偏りのない分析が可能になります。
SWOT分析のメリット・デメリットは?
メリットは、戦略検討時に現状の強み・弱みを整理し、外部環境との関係性から戦略仮説を構築できる点です。デメリットとしては、主観的な評価に偏りやすく、表面的な整理だけで終わってしまうリスクがあります。実行可能なアクションにつなげる工夫が不可欠です。
まとめ
SWOT分析は、企業や事業の現状を客観的に把握し、未来に向けた戦略を構想するための出発点です。しかし、要素を分類するだけで終わってしまえば、戦略に結びつかない単なる自己満足の棚卸しに過ぎません。
重要なのは、問いの設定に始まり、情報収集、構造分析、クロス分析、そして意思決定とアクションへの落とし込みまで、思考のプロセス全体を一貫して設計することです。
特にBtoB領域では、社内外の多様なステークホルダーを巻き込みながら、変化する環境に即した意思決定が求められます。そのためには、強みや機会だけでなく、弱みや脅威にも正面から向き合い、戦略に対する構造的な根拠を言語化する視点が不可欠です。
もしSWOT分析を進めるなかで、情報の不足、解釈の主観化、戦略への落とし込みの難しさといった課題に直面した場合は、当社が提供するリサーチ設計、インタビュー調査、戦略仮説構築の支援をご活用ください。

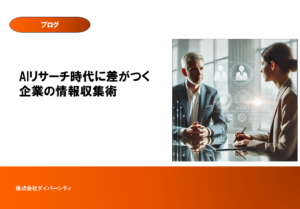
表紙-300x208.jpg)